コラム
一般建設業許可と特定建設業許可の違いと
M&Aの活用
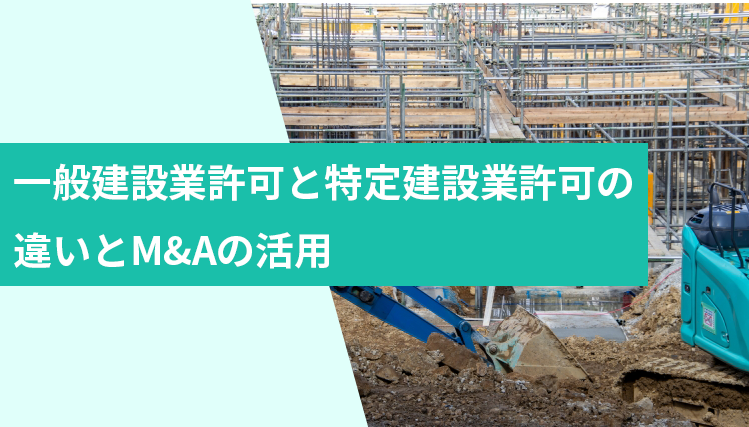
建設業許可の取得をお考えの方から、一般建設業許可と特定建設業許可の
違いはなんなのか、いったいどちらを取得すればいいのか、
とご質問いただくことがあります。
一般建設業許可と特定建設業許可は似て非なるものです。
一般建設業許可とは?
ご存じの通り、500万円以上の工事を請け負う場合は建設業許可が必要となり、
一般建設業許可を取得すれば、その制限はなくなります。
この500万円には消費税・材料費・労務費等も含まれるため、
建設事業を行うにあたっては必須の許可と言えるでしょう。
また、無許可の業者においても500万円(税込)未満の工事や、1500万円(税込)未満の建築一式工事であれば請け負うことは可能です。
特定建設業許可とは?
通常、発注者から直接請負った1件の工事について、
下請代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる
建設工事を施工するときには、一般建設業許可では足りず、
特定建設業許可が必要となります。
つまり特定建設業許可とは、「元請の立場」の場合において、
「一次下請けに出す工事金額」に対して法令で制約がかかっており、
元請けとして一次下請けに出す工事金額で特定許可の要・不要が決まります。
これは二次下請け以降の下請業者として工事を請負う場合には
請負う金額に規制はなく特定建設業許可は必要ありません。
上述の制限から、ある程度大規模な工事を企画、請け負う立場になるには
特定建設業が必要です。しかし、特定建設業許可の取得には
大きなハードルがあるため、多くの方が悩まれています。
例えば、マンションやビルを立てたりなどの「建築一式工事」にて
特定建設業許可を必要となることがほとんどで、不動産業を行う会社が
自社施工も行いたいケースは多くありますが、そのためには特定建設業許可が必要となり、
その取得要件を満たすことが難しい、と断念をされる方が多いのが現状です。
特定建設業許可の取得ハードル
特定建設業の許可を受ける場合には、財産要件に厳しい要件が求められています。
原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表により、
次のすべてに該当しなければいけません。
- 欠損の額が資本金の額の 20%を超えていないこと。
- 流動比率が 75%以上であること。
- 資本金の額が 2,000 万円以上であること。
- 純資産の額が 4,000 万円以上であること。
また、その他に専任技術者においては一級資格者又は監理技術者の
要件を満たした者を設置することに加え、同等の資格者を現場に配置することが必要となっています。
また、直前の決算期において、財産要件を充足する必要があるため、
期中に対策をして、すぐに特定建設業許可を取得するといったことは難しく、
その期の決算を終えまるまで待つか、株主総会において決算期変更の決議を終え、
決算期を前倒しにしてその期の決算を締めてしまうかです。
この方法は、来期以降の経営戦略への影響や納税も発生してしまうため、
慎重な判断が必要です。
M&Aの活用による特定建設業許可要件の充足
これらの要件を創業期や建設業の新規参入法人が満たすことは難しいと言えるでしょう。
特定建設業許可の財産要件については、純資産の4000万円に躓いてしまうような企業などであれば、大きな対策が必要になります。
増資等に想定以上のコストがかかってしまうといったケースは珍しくありません。
貸借対照表の状況によっては数千万から億近い費用がかかることもあるでしょう。
また、一級資格者又は監理技術者に加え、現場に配置する技術者を
確保するのは難しく、人材紹介サービスなどで集めるにしても
1名につき数百万の費用がかかってしまいます。
そこでM&Aを活用し、特定建設業要件を満たした法人を活用し短期間で
大規模工事に参入、といった方法があります。
上述したコストと比較検討し、十分に検討の余地があるようであれば、
その後の特定建設業規模の事業の収益を考えれば、選択肢に入れるべきだと考えます。
M&Aは、規制が多く、人材難が深刻化している現代において、
企業の成長戦略の近道として、当たり前の選択肢となってきています。



