コラム
需要拡大!
解体工事業を始める上での注意点
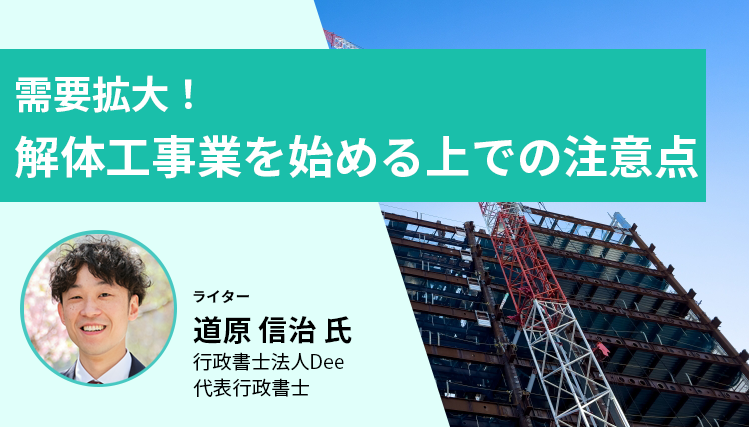
解体工事は堅調な需要のある工事事業です。
高度経済成長期に建設された建物の老朽化や、空き家の増加、都市再開発などにより、今後も継続的に増加すると見込まれています。
その市場の大きさに加え、公共工事の発注も多く、企業の主力事業としては申し分のない分野と言われています。しかし、解体工事は行政手続き上多くの注意点があり、また建設業の中でも法令上の知識が必要となってくる業種と言えます。
今回は解体工事を始める上で注意すべきポイントを項目別でご紹介します。
解体工事とは?
解体工事とは、建物やその他の工作物を破壊し、撤去する工事のことです。主に建て替えや新築工事、老朽化による建物撤去など、様々な目的で実施されます。
解体工事は様々な種類があり、例えば、一戸建て、マンション、ビルなど、建物ごとを解体する工事や建物の内装のみを取り除く内装解体、その他、壁面や建物の特定の部分のみを解体する外部解体・部分解体に加え、アスベストが使用されている部分を取り除くアスベスト除去も解体工事に入るものも有ります。
解体工事にはどんな登録や許可が必要か
解体工事にはどのような登録や許可が必要なのでしょうか?順番に解説します。
【解体工事登録】
解体工事を行う場合には、その工事場所の都道府県において解体工事登録を行わなければなりません。たとえば、東京都と神奈川県の2つの場所で解体工事を行う場合は東京都・神奈川県それぞれで解体工事登録を行わなければなりません。
【解体工事の建設業許可】
工事の請負金額が500万円以上の場合、建設業許可(解体工事業)を取得する必要があります。解体工事は、平成28年6月1日(改正建設業法施行日)から建設業許可に新たに追加された業種です。
令和3年6月30日以前は、「とび・土工工事業」の許可があれば、500万円以上の解体工事を請け負うことができましたが、現在では別途解体工事を取得する事が求められています。
また、解体工事の建設業許可を取得してしまえば、解体工事登録は不要となります。
大きなハードルとなる人材要件について
解体工事登録や解体工事の建設業許可の申請要件のなかで大きなハードルとなってくるのが人材要件です。
それぞれ2つの要件のいずれかを満たす者を社内に在籍させなければなりません。
【解体工事登録】
①要件に当てはまる国家資格者
例 解体工事施工技士、土木施工管理技士、建築施工管理技士など
②8年以上の解体工事の実務経験がある者
【解体工事の建設業許可】
①要件に当てはまる国家資格者
例 解体工事施工技士、土木施工管理技士、建築施工管理技士など
②10年以上の解体工事の実務経験がある者
解体工事の産業廃棄物について
解体工事を行う場合には必ず工事に係る廃棄物が発生します。これは産業廃棄物に当てはまるため、その処分は法令に従って行わなければなりません。産業廃棄物の処分先では処分業の許可が必要なことはもちろんですが、処分先に運搬するだけでも産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になるため、注意が必要です。産業廃棄物の取り扱いは厳しく規制がされており、 安易な気持ちで無許可運搬を実施してしまうと、実施した業者はもちろん、工事の元請まで罰則対象となってしまいます。
行政手続き上の多くの注意点
前述したように、解体工事業を行うにあたりそれぞれの法令・行政手続きをクリアした上で行う必要がありますが、その登録、許可の取得は容易ではありません。特に人材要件を満たすための採用活動は、人材難の建設業界の現在においては難航が予想されるため、 例えば人材紹介業者の転職サービスの活用や、M&Aを活用し、人材資源を持っている会社をその販路・実績ごと手に入れるということも主流となってきています。
\建設業界のM&Aについてお悩みの方はこちらから/
建設業界は不正や無許可での工事を行った業者の処分事例やニュースは年々増えており、後を絶ちません。法令が複雑かつ細かくひかれているため現場の方々の理解が及ばないことや、そもそも情報が届いておらず知らなかった、という事こともあるかもしれません。建設業の適正運営に向け、その企業規模に関わらず、専門家に法令チェックをお願いするなど事業体制の定期メンテナンスの実施をお勧めします。



