コラム
特定建設業許可を持つ会社の
許可更新時のリスクにM&Aや組織再編の一手
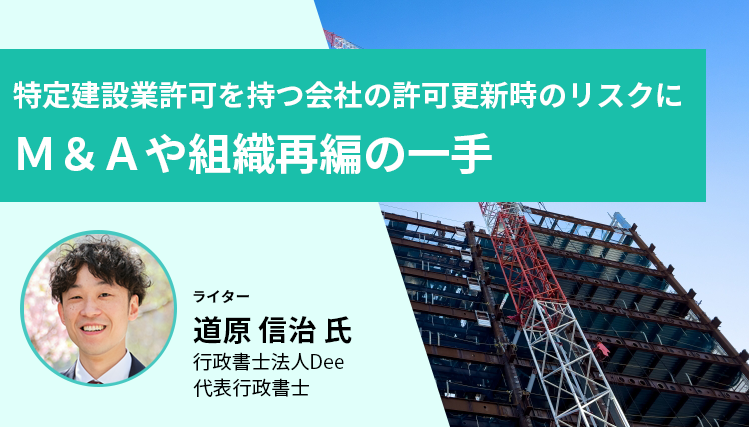
ある程度大きな規模を自社で受注できるようになってくると、特定建設業許可を取得される建設業者は多いかと思います。
一般建設業を持っている建設業者であれば、自社が請け負うことのできる請負金額に上限は有りませんが、自社が元請けとして一次下請けに発注する額が4500万円を超えてしまう場合は特定建設業許可が必要です。
この特定建設業許可を取得するためには一定の財産要件を満たす必要がありますが、特定建設業許可の取得から毎5年、許可の更新を受けなければなりません。
そこで問題となってしまうのが、許可更新時の財産要件です。
このコラムでは、許可更新時の財産要件について詳しく解説します。
特定建設業許可の財産要件
特定建設業許可を取得するには、下記の要件を満たす必要があります。
・資本金2000万円以上
・貸借対照表上の純資産額4000万円以上
・流動比率75%以上
大規模工事を管理することを前提とした許可のため、それなりのハードルの要件となっています。そして厄介な事に、この財産要件は許可更新時にも満たすことが必要となっています。
純資産4000万の維持が難しい
一度崩れた純資産を取り戻すにはそれなりの対策や時間を要することが必要です。
許可取得時に満たしていた財産要件を許可更新時まで維持できなかった建設業者の方からのご相談は、実際多くあります。
その場合、株主や役員からの資金投入や役員貸付金の振り替え等の会計手法上での対策が一般的ですが、中にはM&Aや組織再編を活用して特定建設業許可を維持したケースもありました。
次ではM&Aや組織再編を活用して特定建設業許可を維持したケースについて2つご紹介します。
M&Aや組織再編の活用の例
【例1】M&A+建設業許可承継制度
一つはM&A+建設業許可承継制度の活用です。財務の健全な建設業者を買い取り、不足の資金分を投入することにより財産要件を満たし、
建設業の事業継承を行い、特定建設業許可自体も建設業許可承継制度を使って承継する方法です。
建設事業のM&Aをご検討の方はこちらから
【例1】組織再編+建設業許可承継制度
新設分割で申請法人を設立し、自己資金又は出資してくれる株主を見つけることにより、4000万の資金投入により財産要件を満たし、建設業許可承継制度を使って許可を承継する方法です。
これらの手法はその道に明るい会計士や司法書士・行政書士のサポートが必須と言えるでしょう。
特定建設業許可の更新時の良くある落とし穴
特定建設業許可の更新時のよくある落とし穴としては、「直近期の決算書」を元に財産要件を満たしていることが条件であることです。 そのため、期中の更新時期直前の対策ではどうにもならないという事です。そのため、様々な手法により許可更新時の対策を講じる前提として、かなり余裕をもった時期からの検討・実行が必要になると言えます。
建設業許可の維持には専門家の協力体制が大切
特定建設業許可は都道府県への毎年の決算報告(決算変更届)が義務付けられており、顧問先の会計士や行政書士を通じて申請されている建設業者も多いかと思います。
そのせっかくの毎年の機会をただ作業で終えるのではなく、来るべき特定建設業許可の更新に向け、先回りしてアドバイスをしてくれるような親身な会計士や行政書士を顧問先として選び、許可を管理する体制を構築することはとても大切なことだと考えます。



