コラム
新規参入の際に要注意!
建設業には多くの許可や登録が必要!
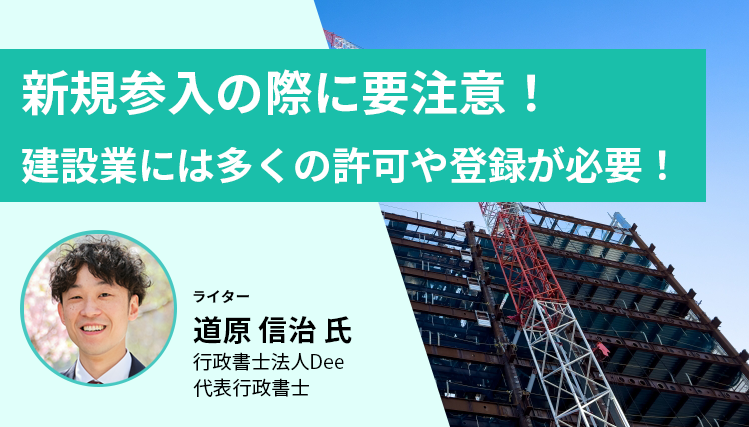
昨今、大企業が本業とのシナジーを求めて、建設業をあらたに始めたり、子会社として建設業者をM&Aしたりするケースが多くみられます。
しかし、建設業は生活のインフラに密接に関わる事業ということもあり、いたるところに法や許可・登録制度が張り巡らされています。
そのため、新規事業などで建設業に参入する際には十分な知識を持っていないと、知らずに違法行為・無許可行為を行ってしまうことにもなりかねません。
このコラムでは新規参入の際に注意すべきポイントを解説します。
許可・登録制度の例
建設業を営む業者が一定の規模以上の工事を請け負う場合に必要な建設業許可は、広く知られていますが、その他にも細々とした制度が存在します。
例えば、電気工事を行う場合は「電気工事業者登録」が必要で、要件として電気工事士資格や実務経験を有した人材が必要です。
この電気工事業者登録は建設業許可の取得の前・後で登録をし直す必要がありますが、無登録の業者は数多く存在しているのが実情です。
また、その他には「解体工事登録」といって、解体工事を行う場合は、建設業許可が必要とならない規模の工事であったとしても、現場のある都県にて解体工事登録を受けなければなりません。
この解体工事登録にも解体工事に係る国家資格者の在籍や実務経験を有した人材が必要ですが、解体工事に係る国家資格の難易度と、求められる実務経験が8年という長期にわたる要件であることから、参入の際に大きな弊害となってしまい、無許可業者も散見されるのが実情です。
隣接異業種の必要な許可
建設業の隣接異業種で必要な許可の代表的な例として、「産業廃棄物収集運搬業の許可」が挙げられます。建設現場から出るゴミが産業廃棄物となる業種と定められています。 そのため、建設現場から出るゴミを処分するために運搬するには、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となり、産業廃棄物処分の許可を持っている処分場に持ち込む必要があります。 建設業現場から出るゴミは、例えば木くず・金属くず・がれきはもちろんエアコン工事の交換エアコンなども幅広く含まれます。
無許可・無登録の弊害
無許可・無登録の弊害は、行政からの罰則です。 その大きさはケースバイケースですが、例えば産廃に関わる違反であれば、違反した下請けだけではなく、元請けまで処分を受けてしまう重いものとなっています。
建設業許可を取得できない。入札にも参加できない。
建設業許可を取得する際に、企業の建設業の5年の経営実績が必要とされます。しかし、電気工事業者登録や解体工事登録を行っていない当該工種での経験は認められないことがほとんどです。 建設業許可を取得できないということは、規模の大きな工事を請け負うことができず、もちろんその先にある公共工事入札にも参加ができません。これは企業活動の根幹を揺るがす事態と言えるでしょう。
建設業への新規参入には注意が必要
上述した通り、無許可・無登録の弊害は大きいものです。特に大企業が建設業に参入する際には細心の注意を払いたいところでしょう。これらの許可・登録制度は企業実績だけでなく、人材の保有資格・実務経験の要件も重要となっており、かつ内容が複雑なものとなっています。 M&Aや内部リソースを活用して建設業への参入を検討される際は、行政書士・弁護士などの建設業に強い専門家に相談し、知識の補完を図ることも大切です。



